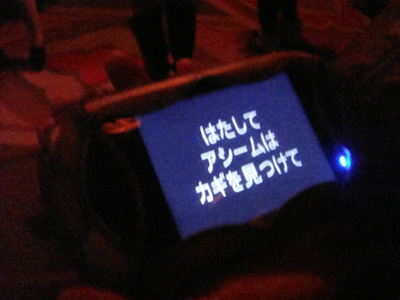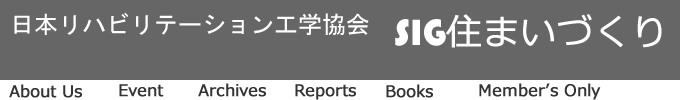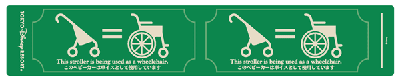イベント報告
東京ディズニー・リゾート見学会
SIG住まいづくりメンバー16名が参加し、2010年11月19日の午後に行われた。まずオリエンタルランド本社会議室において、経営戦略本部理事の望月様と野口様から、ユニバーサルデザインに関する取り組みをお聞きし、その後ディズニーシーに入場し、施設内の工夫や設備などを見学させていただいた。
ユニバーサルデザインの取り組み
まず我々が一番驚かされたのは、「私たちはユニバーサルデザインやバリアフリーを考えてはいない。すべてのゲスト(TDRではお客様をゲスト、スタッフをキャストと呼んでいる)がVIPであり、ゲスト一人ひとりに楽しんでもらうために何が必要かを考えているだけ」というコメントであった。高齢者も障害者もゲストであり、他のゲストと同じように楽しんでもらえるということで、TDRでは障害者割引がない。では、どのような取り組みを行って来られたのかを、お聞きした話からまとめてみた。
1983年にディズニーランドをオープンしてから7年間は、とにかく運営していくことで精一杯で高齢者や障害者への配慮どころではなかった。それでもアメリカの基準でトイレなどの設備を造ったので、スペースや扉の幅員など進んでいる部分が多くあった。少し余裕ができてきたころ、E&Cプロジェクト(現・財団法人共用品推進機構)のセミナーで視覚障害者の話を聞いたことがきっかけで、10名の視覚障害者にアトラクションを楽しんでもらい、後で楽しかった順番を教えてもらった。その結果を分析し、人気の無いアトラクションを楽しんでもらえるものにする工夫を考えるところから始めることになった。
TDRの工夫
【触知図】
日本点字図書館に意見を聞いたが、一般的な触知図ではパーク空間の楽しさが伝わ
らないと判断し、独自にアレンジして制作。
床材を4つのテーマパークごとに、テーマを連想させるテクスチャーで表現。使っている素材は壁クロス。壁クロスには様々なテクスチャーがあって、選ぶのに困らなかったとのこと。我々が見ても楽しそうな触知図に仕上がっている。共用品なので、いろんな方が触って壊れてしまうといけないので、普段はカバーを被せてあるが、視覚障がいのある方がいらっしゃった場合は、キャストがカバーを外して触っていただく。
|
 |
【インフォメーションブック】
身体障がい、視覚障がい、聴覚障がいのあるゲストに事前にお送りする。CD版もある。利用できるアトラクションの紹介や、アレルギーのある方のために食べ物に使っている食材の情報提供、その他手話サービスや音声ガイドシステムの利用案内など。
|
|
【ストーリーペーパー】
視覚障がい、聴覚障がいのあるゲストにアトラクションのわかりづらい内容をある程度事前に把握しておいていただくことで、より楽しんでいただくためのツール。ストーリーペーパーは一般来場者でも手に入れることができるとのこと。
入り口ですべてを渡してしまうと楽しみが減るので、アトラクションに入った人だけ、またアトラクションを進むにつれて一枚ずつ渡すなど、楽しむための工夫がされている。
|
 |
【携帯触知図】
少し大きいが、音声ガイドシステムと一緒に利用すると便利。
|
|
【キャラクタースケールモデル】
生下時から視覚障がいのあるゲストには、キャラクターがどんな形をしているのかもわからないため、メインキャラクターのスケールモデルを取りそろえ、入場前に触っていただくことで、キャラクターの特徴やかわいらしさを理解していただくためのツール。
ボタン、燕尾服の様子まで立体的に表現している。
|
 |
【ビークルのスケールモデル】
各アトラクションで乗るビークルの模型を準備。こんな乗り物に、ここから乗り込んで、ここを掴んで乗る、というような概要を事前に把握していただくためのツール。視覚に障がいのある方が、乗り込む前に不安を感じないように、触って確認する。スムーズな乗車にも役立つ。木製で手触りもよい。
すべて手のひらに乗る程度のサイズになっている。リレーション(案内所)と各アトラクションに1つずつ置かれている。
|
 |
【水域転落防止手すり】
手すりの高さは1200mmとの指導があるが、子どもや車いす利用者の目の前に来ることとなり、ショーの妨げになってしまう。ショーが始まる直前に「ミッキーからの贈り物だよ!」など言いながら、一斉に倒す。油圧シリンダーが入っていて、ゆっくりと降りるような工夫がある。
|
 |
【車いす用ビークル、車いす専用乗降場】
アトラクションによって車いすに乗ったまま乗降できるビークルがある。また、ゆっくり乗り降りしていただけるように、他のゲストと別の乗降場があるアトラクションがある。
TDRで用意した車いすに乗り換えてもらうのは、ビークルの固定装置に固定しないといけないためである。別の入り口から入った車いす使用者の乗ったビークルは、途中で一般のものと合流、終了後も途中から別のルートに誘導されるようになっている。
車いす使用者の部分だけ床を下げて、椅子に座っている人と頭の高さを揃えている。
|
TDRのHPをご覧ください |
【バギータグ】
子どもが小さい時は障がいがあっても車いすではなくバギーに乗せているケースもあり、事前に目印となるタブをバギーにつけている
と、車いす鑑賞エリアを利用できる仕組み。以前は赤色のタグであったが、危険を意味するのはおかしいということで緑になった。
|
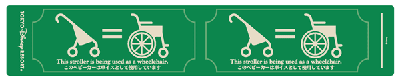
TDRオフィシャルホームページより |
【水飲器】
アトラクションのビークルの安全装置のモックアップで事前に説明をして、スムーズに乗車いただく。
ゲストの背の高さや体格によって、アトラクションの安全装置が使えない場合があるため、事前に試すことのできるモックアップを他のゲストには分からない場所に設置している。事前に確認することで、多くのゲストがいる乗り込み時に諦めるという恥ずかしい思いを無くすことができるとのこと。
|
 |
【字幕テロップ】
アトラクションによっては、字幕によってストーリーを解説。状況に応じて、英語や中国語も流すことができる。
あらかじめ入っている台詞であるので、キャストのアドリブにはついていけない。
ゲストの国に合わせて、英語と中国語の用意もある。
|
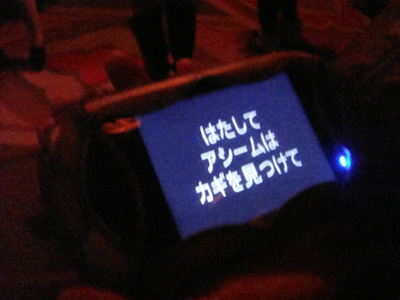 |
【アトラクションの危険度表示】
ビークルが回転するようなアトラクションについては、入り口でビークルがどのような動きをするかを視覚的に表現するように工夫されている。写真の中央(時計の下)に回転するレールを点滅する照明で表現し、ビークルの動きを示している。
|
 |
【エレベーター】
アトラクションやパークのテーマに沿って作っているため、どこにあるか分かりにくい。キャストの誘導が無いと入れないようになっている。テーマパークであるので、バリアフリーよりもテーマ性を重んじているが故である。
|
|
【音声ガイドシステム(TDSのみ)】
視覚障害者誘導用ブロックの敷設は、TDSの案内所の1か所だけである。その代わりに、パーク内70カ所にサインポストを設置。微弱電波でイヤホンに音声を流し、今いる場所やアトラクションのストーリー、トイレの場所などを視覚障がいのあるゲストに伝えている。
|
 |
【手話ピン】
手話を勉強している人には、ピンを着けて分かるようにしている。キャストが自ら勉強している。現在約100名いる。
|
|
【食事】
園内は食中毒の危険を回避するために弁当の持ち込みを禁じている。
障害のある人には、レンジやフードプロフェッサーの使用ができる、レトルト食品や弁当の持ち込みができるなどの配慮がある。
|
|
| |
|
文・写真:
梶谷知史(積水ハウス株式会社 医療・介護推進事業部)
糟谷佐紀(神戸学院大学総合リハビリテーション学部) |