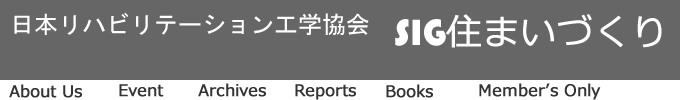「毎日使うトイレをとことん考えてみよう!」報告
■日時: 2008年8月30日(土) 10:30~17:00
■会場: 新潟市中央区島6-1
朱鷺メッセ:
新潟コンベンションセンター3階
中会議室
■主催: SIG住まいづくり
■後援: 日本福祉のまちづくり学会
■内容:
| トイレコンテスト報告&なんちゃってバリアフリーコンテスト報告 | |
午前は、これまでSIG住まいづくりが行ってきたコンテストの報告を、糟谷事務局長が行いました。 |
|
| 基調講演 トイレあれやこれや | |
午後からは、東洋大学ライフデザイン学部教授の川内美彦さんから「トイレ、あれやこれや」というタイトルでお話しいただきました。多機能トイレの変遷について、車いす使用者を対象として作ってきた経緯がありますが、最近では多くの機能を取り入れたトイレとなってきたために、オストメイト、ベビーカーを使用する親など利用対象者が増えてきました。そのために、常に誰かが使用している状態となり、これまで待たなくても使用できた車いす使用者からは不満の声も上がってきています。 |
|
| 報告 プライベートトイレ | |
続いての事例報告では、まず佐賀大学大学院准教授の松尾清美さんから、プライベートトイレについてご報告いただきました。多様な障害レベルの人がどのようにして便器に近づき、乗り移っているのかを動画を交えながらわかりやすく解説していただきました。便器へのアプローチの方法で必要なスペースやレイアウトが変わること、住宅改造の規模も変わることがわかりました。また、高位頸髄損傷者などが行っている自己導尿についても、使用する器具や使用するときの姿勢など、リハビリテーション工学分野の情報が伝達され、参加者にとって初めて知る情報が多かったと思いました。 |
 |
| 報告 パブリックトイレ | |
| 事例報告の第2弾では、TOTO株式会社の真島香さんから、パブリックトイレについてご報告いただきました。現在、商業施設のトイレに求められている視点を、ユニバーサルデザインと環境への配慮の二面から解説し、TOTOの01シリーズというスタイリッシュな多機能トイレの新製品情報と、今後の課題についてお話されました。 ユニバーサルデザインとしては、荷物への配慮と女性のお化粧への配慮、親子連れ・子供への配慮、そして高齢者・障害者への配慮について調査データに基づいて報告いただきました。障害者への配慮については、動作検証のビデオを使いながら説明され、昨年策定された操作系の配置のJISについて解説いだきました。 |
 |
| パネルディスカッション | |
| パネルディスカッションでは、基調講演の川内さん、事例報告の松尾さん、真島さんに加えて、TOTO株式会社UD研究所初代所長として、様々な商品開発、検証実験にかかわってこられた竜口隆三さん(現在は西日本工業大学デザイン学部教授)に加わっていただき、SIG住まいづくりの相良代表のコーディネートで進められました。 |  |
多機能トイレにオストメイト対応のシンクがあるが、内部障害は見かけ上わからない障害なので、使って出てくると待っている人に文句を言われるというトラブルになることが多いという話があがりました。オストメイト専用の便房を設ければ小さな空間で済むのではないかという意見に対し、オストメイトであることを公言している人と隠したい人があるので、それだけでは解決できないのだという意見がありました。 |
|
終了後のアンケートでは、とても勉強になった、もっと多くの人に聞かせたい、トイレの次は浴室についてとことん話したい、グループワークのような参加型も期待したいなど多くのご意見をいただきました。 |
 |